山本義徳さんの101理論はご存知ですか?
家トレに活用出来そうと思い実践してみました。
山本 義徳(やまもと よしのり、1969年 – )は、静岡県出身の日本のボディビルダー、タレント、トレーニング指導者。 静岡県立静岡高校卒業。早稲田大学政治経済学部卒業。日本ボディメイキング振興協会所属。
フィットネスジム『ミッドブレス』にてゼネラルアドバイザーを務めていたが、2012年5月をもって契約を満了。 現在、『T-BODYMAKEトレーニングジム』や東京都体育館を利用したパーソナルトレーナーとして活動している。 wikipedia
101理論とは(インタビュー記事)

正しくお伝えするためにインタビュー記事をそのまま参照します。
-- 食事もトレーニングも理論がたくさんありますよね。選択が難しい。
トレーニングはストレスへの応答反応ですから、どんなストレスであってもある程度は発達するんです。つまり少しぐらい間違ったトレーニングでも発達するんですよね。
いろんなトレーニングが満ちあふれていますけど、多少間違っていてもそれなりの効果は出るので玉石混交になってしまうんです。
-- 現状でしうる完璧なトレーニングとしてはどのようなものがありますか?
自分が提唱しているのは「101の理論」です。身体の能力を100としますと、それに対するトレーニングの刺激は101でよく、120、130の刺激を与える必要はないという考えです。
要は筋肉の発達するスイッチを押せるかどうかですので、101のストレスが与えられればそれでスイッチは押される。120、130のストレスはスイッチを強く押し続けるようなもので、101以上の刺激は無駄で回復を遅らせるだけという考えです。
具体的には、できるだけ少ないトレーニング量で最低限の刺激を与えましょうというトレーニング方法で、セット数に関して言えば1つの種目について1セットでも基本は十分です。
スクワットのような大きい動きの種目は10レップス行うのに30秒ぐらいかかります。
一方、前腕の小さな動きだと10レップスに10秒ほどしかかからない。同じ10レップスでも筋肉が緊張している時間は違うわけで、部位によってレップ数も考えなくてはいけません。
-- ひたすらたくさんやるよりも、そのぐらいでいいんですね。
101の刺激、ポジティブ・フェイラーというんですけど、自力でできなくなるまでですね。
ポジティブは上げる、ネガティブは下ろす、自力で上げることができなくなるところまでやればいいということで、補助して何回も追加してやるのは120、130の刺激を与えるばかりで回復が遅れるだけ。
だから最低限の刺激を与えて回復も早め、そのぶん頻度を高くすると短い期間で発達できるということです。
-- 101なら1セットでいい。
理想的にはそうです。ただ、1セットで101の刺激に至るのはなかなか難しいので、たとえば1セットを3種目、トータルでやっていく感じになると思います。
トレーニングによる刺激で筋たんぱくの合成が高まるのはだいたい48時間後ぐらいまでの間。2日間ぐらいは確実にトレーニングの効果が出ているので、中3日くらいあけておけば十分で、理想的には1セットを週2回ということですね。
トレーニングを始めたばかりで1セットで90ぐらいの刺激しか与えられない人は2セット行うことで代用してもいいと思います。
-- 自分の身体でどこまでが101なのか、130なのか。
たとえば筋肉痛の強さです。ほんの少し筋肉痛がくれば、それでもう十分。次の日に筋肉痛がでるのは120、130。その比較なら分かりやすいと思います。
自力で上げられなくなったのをトレーナーが補助して続けさせるのはあまり良いやり方ではないですね。http://physiqueonline.jp/fitness/page2127.html
上記の101理論のメリット、デメリット
101理論を私なりに解釈してまとめてみました。
- 自分の身体能力を100としたとき101のストレスを与えればいい
- 補助なしで行える刺激で十分
- 理想は1種目1セット
- インターバルは4分(動画を参考)
- 軽く筋肉痛が起きる程度の刺激
101理論は、身体能力を100としたとき101のストレス(刺激)を
与えるだけで筋肥大は可能ということ。
では、101理論のメリット、デメリットはどんなことが
考えられるのでしょうか?
メリット
・私が今まで基本としてきた1つの筋肉部位に対して5種目
とかではなく、1種目で十分刺激が与えられることができる(あくまで理想です)
・補助なしで行える刺激で十分に筋肥大できる。
・トレーニング時間が短い(75分以内がいいとされています)
デメリット
・重量設定が難しい
・初心者向きではない
たしかに、やや難易度が高いトレーニング方法な気がしますが
メリットの方が明らかに大きいと思います。
これは、「とりあえず試すしかない」と思いさっそく実践してみました。
101理論を実践してみた
私が行ったのは、大胸筋のダンベルのみの種目です。
- インクラインダンベルフライ
- ダンベルフライ
重量設定は、フォーム重視で行うことがいいという話でしたので
15回出来るであろう15キロに設定しました。
101理論は初めてなので、2種目、2セット行うことにし
さっそく実践してみました。
インクラインダンベルフライ
まず、重り無しでフォームと大胸筋上部の筋肉の確認を行い
10キロのダンベルでウォーミングアップをします。
そして本番セット15キロで15回めざして行いました。
これを2セット。
ダンベルフライ
こちらも、フォーム確認をしてから本番セット。
インクラインで新しい刺激で効きか良かったので12キロに落として2セット。
実践してみた感想
種目数が減るということで半信半疑で行ってみましたが
思いのほか効きが良かったことにびっくり。
2セットで十分目的の筋肉には効かすことができました。
筋肉痛も軽くきたので101理論では、100を超えれたということで
いいと思います。
セット間のインターバルを4分間と長めにとることで2セット目で余力なく
力を出し切れた印象です。慣れないうちは2セットで組んだ方がいいかもしれません。
この種目数なら、もう1部位増やしてもいいかもしれませんね。
私なら弱点の大胸筋と肩を週2回行い強化していく感じでやってみます。
こちらも参考にしてみてください
継続してみての感想もアップしていきますのでよろしくお願いいたします。
ちなみに、山本義徳さんの筋トレの分割は「胸、背中、腕」「足、肩」で分けているそうです。
参考までに!
では、ベイトでした。
101理論のオススメの記事



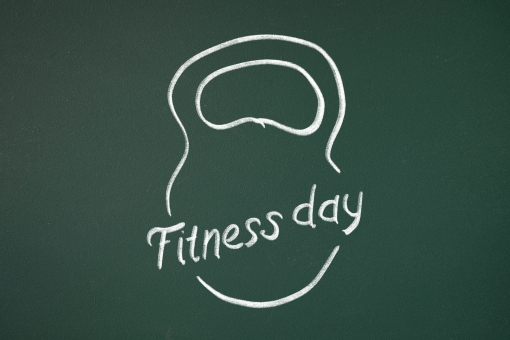






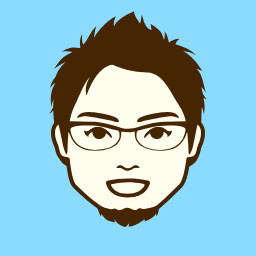


コメント