
※ここに掲載した検査項目は、血液検査、尿検査後に手渡される「検査結果報告書」の中から、一般的な検査項目を抜粋し説明したものです。
病気の診断は、検査だけではなく問診、診察などとともに総合的に判断されますので、検査結果の目安にして下さい。
血液成分の濃度は、疾患だけではなく年齢、食事や運動などいろいろな条件で変動します。
数値に疑問を感じたならば、担当医に相談することをお勧めいたします。
※ブックマークをして検査結果の確認の際に、ご利用ください。
健康診断からわかる!血液、尿検査結果の早見表
| 表示名 | 項目名 | 検査項目の説明 | 高値で可能性のある疾患 | 低値で可能性のある疾患 |
| AST | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | 肝臓や筋肉・赤血球に含まれ、炎症などで細胞が壊れると血中に流出します | 肝炎、脂肪肝、心筋梗塞 | |
| ALT | アラニンアミノトランスフェラーゼ | 主に肝臓に含まれ、肝臓や胆道の炎症などで細胞が壊れると血中に流出します | 肝炎、アルコール性肝障害、脂肪肝 | |
| LDH | 乳酸脱水素酵素 | 体内の多くの細胞に存在するので、細胞が壊れると血中に増加します | 肝臓・心臓・筋肉・血液の疾患 | |
| ALP | アルカリホスファターゼ | 肝臓、胆道、骨などにある酵素でこれらの障害や成長期でも増加します | 肝臓・胆道疾患・骨疾患 | |
| r-GTP | r-グルタミルトランスプチダーゼ | 胆汁の流れ(肝臓→胆道→腸)の障害やアルコールの多飲で増加します | アルコール性肝障害、脂肪肝、肝硬変 | |
| CHE | コリンエステラーゼ | 肝臓の機能をよく反映し、重症度の評価に役立ちます | 脂肪肝、ネフローゼ症候群 | 肝炎、肝硬変、栄養不良 |
| AMY | アミラーゼ | すい臓や唾液腺で作られる酵素で、すい臓疾患の検査に役立ちます | すい炎、耳下腺炎、肝機能障害 | 膵がん、重度糖尿病 |
| CK | クレアチニン・ホスホキナーゼ | 心筋や骨格筋などの組織・細胞の障害を反映します | 心筋梗塞、心筋炎、筋肉疾患 | |
| Na | ナトリウム | 体内の水分の調整に重要な役割を果たしており、尿・汗・便として排出されます | 脱水。糖尿病、クッシング症候群 | 浮腫、下痢、嘔吐 |
| K | カリウム | 神経の興奮や、体・心臓の筋肉の働きを助ける物質です | 炎症、外傷、熱傷 | 下痢、嘔吐、クッシング症候群 |
| Cl | クロール | 主に食塩として摂取され、腎臓を通って尿中に排出されます | 脱水、腎不全、塩分過剰摂取 | 尿崩症、アジソン病、嘔吐 |
| Ca | カルシウム | 骨や歯に大量に含まれ、血液中のカルシウム濃度は一定にされています | 副甲状腺機能亢進症、悪性腫瘍 | 副甲状腺機能低下症、ビタミンD欠乏 |
| BUN | 尿素窒素 | 体で使われた物質の老廃物で、腎臓からろ過され尿中に排泄されます | 腎炎、脱水、多量のたんぱく摂取 | 肝不全、腎不全、妊娠 |
| CRE | クレアチニン | 体内で使われた物質の老廃物で、腎臓からろ過され尿中に排泄されます | 腎不全、脱水、心不全 | 妊娠、糖尿病初期 |
| UA | 尿酸 | プリン体が分解されてできた老廃物で、尿中に排泄されます | 痛風、無症候性高尿酸血症、腎不全 | 腎性低尿酸血症、尿酸低下薬 |
| T-CHO | 総コルステロール | 血管の強化・維持に重要ですが、多すぎると生活習慣病の原因となります | 糖尿病、肝硬変、すい炎 | 肝硬変、栄養障害、白血病 |
| TG | 中性脂肪 | 血液中の脂肪の一種で、高いと動脈硬化や心臓病、脳卒中の危険因子となります | 肥満、食べすぎ、飲酒 | |
| LDL-C | LDL-コレステロール | 悪玉コレステロールのことで、動脈硬化性疾患の直接的な危険因子と考えられます | 高コレステロール血症、ネフローゼ症候群 | β低リポ蛋白血症、肝硬変、肝炎 |
| HDL-C | HDL-コレステロール | 善玉コレステロールのことで、動脈硬化性疾患の危険因子の有無を調べます | リパーゼ欠損症、多量飲酒、正常女性 | 高脂血症、肝硬変、肥満 |
| T-Bil | 総ビリルビン | 赤血球が肝臓・ひ臓などで壊された後のヘモグロビンが胆嚢(たんのう)でビリルビンに変化します | 黄疸(おうだん)、肝炎、溶血性貧血 | |
| TP | 総蛋白 | 血液中の様々な総蛋白の総量です | 脱水、多発性骨髄腫、悪性腫瘍 | ネフローゼ症候群、出血、肝障害 |
| CRP | C反応性蛋白 | 炎症反応を示す蛋白です | 感染症、悪性腫瘍、炎症性疾患 | |
| 血糖 | グルコース | 血液中のブドウ糖のことで、全身のエネルギー源になっています | 糖尿病 | インスリン・経口糖尿病薬の使用 |
| HbA1c | グリコヘモグロビンA1c | ヘモグロビンと糖が結合したもので、過去1~3か月の平均血糖値を反映します | 糖尿病、腎不全、アルコール多飲 | 悪性貧血、肝硬変、妊娠 |
健康診断応用編!生化学検査、血液検査、尿検査を知ろう

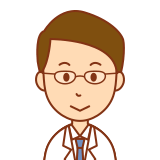
聞きなれない「生化学検査」の説明と、血液検査、尿検査ごとに別けた詳細を載せておきます。
生化学検査とは?

生化学検査とは、どんなものなのでしょうか?
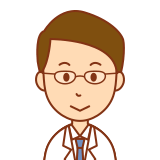
生化学検査は、血液や尿の中の含まれている多くの化学物質を測定するもので、それによって身体の健康状態、各内臓関係のほとんどのチェックをできる重要な検査の一つです。
血液検査とは?

血液検査とは、どんなものなのでしょうか?
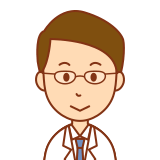
血液は、酸素や栄養分を各組織や細胞に運ぶとともに、二酸化炭素や老廃物を体から運び出す働きをしています。血液検査とは赤血球や白血球、その他の成分や数、比率等を検査し、異常がないかチェックする検査です。
尿検査とは?

では、尿検査とはどんなものなのでしょうか?
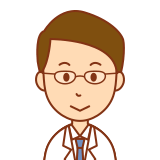
尿は腎臓で作られ、尿管、尿道を経て体外に排出されます。その成分を調べると、腎臓や泌尿器系臓器の状態の評価に役立ちます。また、膀胱や尿道にできた腫瘍についても調べることができます。
生化学検査、血液検査、尿検査 からわかること
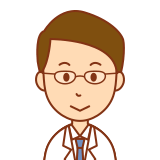
各検査でわかることを、それぞれ紹介しておきますね!
生化学検査でわかること
「生化学検査」では、肝臓、心臓、糖代謝、腎臓、膵臓、脂質などの状態をチェックすることができます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
AST:肝炎・アルコール性肝障害や脂肪肝などで高値となります。心臓疾患でも高値を示すことがります。
ALT:肝臓疾患(肝炎・肝硬変・脂肪肝など)で高値を示します。
rGT:肝臓疾患や胆のう疾患で高値を示します。アルコールを多飲すると高くなります。
ALP:肝臓や胆道・骨などに異常がある場合(肝炎、肝がん、胆管結石、骨のがん転移など)で高値となります。
TB:肝臓・胆道に異常があると黄疸(皮膚が黄色くなる)が現れ、高値となります。
LD:肝臓、心臓、肺、血液疾患、悪性腫瘍で高値となります。
CHE:脂肪肝、腎疾患、甲状腺機能高進症などで高値になり、肝炎、肝硬変、栄養不良などで低値となります。
CK:心筋梗塞や骨格筋の損傷で高値を示します。激しい運動でも高値となります。
GLU:高値の場合、糖尿病が疑われます。食事の影響を強く受けます。
HnA1c:過去1~3か月程度の血糖の平均状態を表します。高値の場合、高血糖が続いたことを示し、糖尿病が疑われます。
UN:腎機能の指標で、腎炎や尿毒症などで高値を示します。脱水や消化管出血などでも高値となります。
CRE:腎機能・筋肉量の指標となり、腎炎や腎不全で高値となります。筋肉質の人や肉食は続いた場合も高値となります。
UA:痛風・糖尿病・腎不全などで高値を示します。
AMY:すい炎や耳下腺炎で高値を示します。
TC:総コレステロールのことで、高脂血症、動脈硬化などで高値になります。
HDL-C:善玉コレステロールと呼ばれ、高脂血症、動脈硬化などで低値になります。
LDL-C:悪玉コレステロールと呼ばれ、高値では、脳梗塞、心筋梗塞等の動脈硬化につながります。
Na,K,Cl:電解質のバランスの指標で、下痢や嘔吐で低値になります。脱水などで高値となります。
TP:栄養状態や肝臓、腎臓の機能の指標で、脱水で高値となり、肝臓の異常、悪性腫瘍や感染症、栄養不足で低値になります。
血液検査でわかること
赤血球、白血球、血小板など血液の状態をチェックできます。
RBC:血液の大部分を占めており、体の細胞に酸素を運ぶ重要な役割があります。少ないと貧血、多いと多血症が考えられます。
Hb:赤血球に含まれており、酸素運搬の中心の役割を果たしています。貧血で低値となります。
Ht:血液中に占める赤血球の割合です。貧血や多血症の重症度が分かります。
MCV:赤血球1個あたりの大きさの平均値です。貧血の原因の手がかりとなります。
MCH:赤血球1個あたりのヘモグロビン量の平均値です。貧血の原因の手がかりになります。
MCHC:赤血球1個あたりのヘモグロビン濃度の平均値です。貧血の原因の手がかりになります。
WBC:病原菌から体を防御するための主役となります。炎症や感染症、心筋梗塞、白血病などで高値となります。
PLT:血小板は止血するのに重要な役割をします。その数が減ると出血しやすくなります。血液疾患や肝臓疾患で低値となります。
PT:プロトロンビン時間と言います。活性値(%)と時間(秒)で表します。活性値が低下の場合、出血傾向にあることを示します。
APTT:活性化部分トロンボプラスチン時間といいます。出血傾向がある場合や肝臓疾患、および遺伝子性疾患の代表である血友症などで高値となります。
フィブリノーゲン:止血に必要なタンパク質です。肝臓の障害などでも低値となり、炎症や悪性腫瘍などで高値となります。
尿検査でわかること
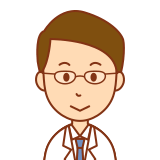
定性検査は、尿にどんな物質が含まれているかを調べる検査です。結果は(+)か(-)で報告します。(強さによっては+/-~+++まで)
色調:通常は淡黄褐色、血尿で赤色になります。
清濁:通常は清で、混濁の原因は細菌や結晶、その他の混入物などによります。
比重:通常は1.010~1.025、脱水などで尿量が減ると高くなり、尿量が減る疾患(尿崩症など)では低くなります。
PH:通常は弱酸性です。痛風などで低値(酸性)になり、尿路感染症などで高値(アルカリ性)になります。食事や運動の影響を受けやすいです。
糖:通常は陰性、糖尿病で(+)となります。
ケトン体:通常は陰性、陽性→糖尿病、妊娠中毒症、発熱、嘔吐で(+)となります。
蛋白:通常は陰性、腎疾患で(+)となります。健康でも運動後やストレスで(+)となることもあります。
ビリルビン:通常は陰性、(+)であれば肝臓や胆道疾患の存在を推測できます。
潜血:通常は陰性、赤血球があるか(血尿であるか)の検査です。尿路結石症、膀胱がん、膀胱炎、腎疾患などで(+)となります。
ウロビリノーゲン:通常は(+/-)です。肝炎、肝硬変などで(+)となり、黄疸などで(-)となります。
亜硝酸塩:通常は陰性、尿中に細菌が存在すると(+)となり尿路感染症の可能性があります。
白血病反応:通常は陰性、膀胱炎や腎孟腎炎、感染症などで(+)となります。
以上が生化学検査、血液検査、尿検査でわかることでした。自身の「検査報告書」と照らし合わせて確認してみてください。
検査結果に疑問があれば、担当医に「病気の可能性」がないかを確認しましょう。40才を以上の方は病気のリスクも高くなりますので、定期的な人間ドック(平均40,000円)の受診も考えていかなければなりません。
ガンも早期発見で完治する確率が大きく変わりますので、ガンを早期発見できる人間ドッグ(腫瘍マーカ、胃カメラ、腹部エコーなど)はお勧めです。
全国の病院を対象に、人間ドックをご予約、検索できるフォームを貼っておきますので、お近くの病院又は健康管理センターを検索してみましょう。
「人間ドックに行く時間がない」という方には、家に居ながら人間ドックを受けられる”おうちでドック”(10,000~30,000円)もございますので、そちらのご使用もご検討ください。
【検査できるもの(一部)】
- ガン(乳がん、子宮がん、食道がん、大腸がんなど)
- 糖尿病
- 動脈硬化
- 腎疾患
- 肝臓疾患
- 痛風
- 尿管結石
- 脂質代謝異常
- 肥満度
- 栄養障害
「病気かも・・・」と不安でいることは、心にも体にも悪影響を及ぼします。「異常がない」とわかるだけでも精神的にラクになりますので、心のモヤモヤを取り除き、晴々した毎日を送るためにも、人間ドックを受けましょう。
血液、尿検査結果の早見表をもとに、体調管理に役立てよう
健康診断の結果、改善すべき項目が見つかったのであれば、大きな病気になる前に早めの対処をしましょう。
改善すべき点は、
- 食事内容
- 運動
- ストレス
この3つの内、食事と運動は自分の努力次第で改善できます。運動が苦手な方は、負担の少ないホームトレーニングから始めてみてはいかがでしょうか?
初心者にもわかりやすく解説していますので、是非参考にしてください。
生活習慣病の原因「内臓脂肪」についての記事はこちら!
内臓脂肪が落ちないのはなぜ?内臓脂肪がつく原因と落とす方法を解説
【運動が苦手!でも皮下脂肪を落としたい方はこちら】
皮下脂肪を3か月で落とす食事管理|たった1度の計算でみるみる痩せる
筋トレ初心者様に知っておいてほしいこと!
【女性の方はこちらの記事を多く読んでいます】
【30代女性は必見】空き時間を使い、自宅ヨガで健康を手に入れよう!

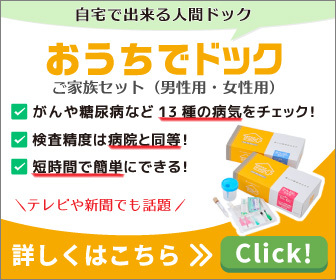


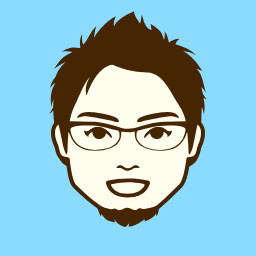


コメント