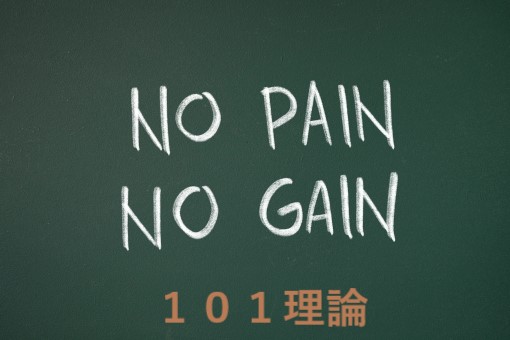
「101理論」実践中のベイトです。
山本義徳さんの101理論を実践していくにあたって、筋トレに対しての考え方が大きく変わり始めました。
家トレに活かすために、日々、101理論や山本義徳さんの著書などに目を通しています。
ここで、筋トレメニューの組み方などを大きく変えてみようと計画しています。
私なりに101理論から受け取ったメッセージをご紹介していきたいと思います。
101理論から学んだ改善点

私が101理論から学んで「改善しなければ」と思った内容をいくつかあげていきます。
そもそも筋肉を追い込みすぎなのでは?
山本義徳さんの101理論では、「自分の身体能力を100としたとき101の刺激で十分」という説です。
筋トレ歴やマッスルコントロールで101の刺激まで到達するには個人差がでますが、翌日軽い筋肉痛が来るくらい刺激を入れることが目安とおっしゃっています。
多くのトレーニーは何となく「このくらいなら筋肉痛になるな」というのは、感覚で分かると思います。(わからない方は回数を重ねると分かってきます)
自分の今までのトレーニングを考えると、翌日「筋肉痛が酷くて肩を上げれない」など良くありましたが「筋肉痛は追い込めた証拠」などと勝手に満足していました。
そもそもこれはやりすぎのサインなのではないかと感じる様になりました。
101理論を実践していく上で「101以上の刺激は回復を遅らせる」とありますので、「無理な追い込み」は必要ない、もしくは毎回でなくてもいいという判断に至りました。
後は、実践をしてみて体感しながら変更していこうと思います。
101理論から学んだ、筋トレメユーの組み方
筋肥大だけを目的にトレーニングしている場合、速筋繊維を多く使い筋肥大させていく訳ですが、インターバルの長さやセット数の数、メニューの組み合わせによっては遅筋繊維を多く使う持久力のトレーニングに切り替わるというお話もありました。
多くのボディビルダーは速筋繊維を主に使うようなトレーニングを行っている(高重量トレーニング)のに、実は遅筋繊維がかなり発達しているということが知られています。
これはトレーニングの量が多いこととともに、短めのインターバルをおいてセットを繰り返すことによりミトコンドリアや毛細血管の発達が促され、さらに疲労物質の蓄積や筋細胞内環境のダイナミックな変化が起こることにより、トレーニングにおける物理的刺激で速筋が発達するのに加え、化学的刺激が加わって遅筋繊維も発達するということで了解されています。
一部抜粋:山本義徳さんのブログ
物理的刺激=高重量:低レップの刺激
化学的刺激=低~中重量:高レップ刺激
ということを踏まえると、1週ごとに「物理的刺激のトレーニングの日」と「科学的刺激のトレーニングの日」を分けてメニューを組んだ方が効率的ということだと感じました。
私は今まで、高重量種目の後にパンプさせる種目を組み合わせてメニュー構成をしてきましたが、各週によって「高重量トレの日」とパンプ目的の「低~中重量トレの日」に分けて行うことにしました。
山本義徳さんのお話ですと“筋肥大にはどちらの刺激も必要„とのことですので日を分けて筋トレメニューを考えていきます。
これも自分に合うかは実践を繰り返すしかないので、また実践報告していきます。
101理論から学んだ、インターバルの長さの改善

私は今まで、インターバルは長くて1分位にしてきましたが、このインターバルの長さも改善すべきと思いました。
先ほどの山本義徳さんのブログ記事でも少し触れていましたが、インターバルの短いセットを繰り返すことで、速筋と共に遅筋も多く使ってしまうトレーニングになるということ。
個人的には、筋肥大を主に狙いたいという目的があります。
ということは、「物理的刺激の日のトレーニング」のインターバルは長めの4分前後。
「化学的刺激の日のトレーニング」のインターバルは2~3分位の設定にしてみました。
インターバルの時間の設定は、山本義徳さんの発言などから設定しました。
これを実践で繰り返して効果を確かめていきたいと思います。
101理論から学んだ、セット数の基準

101理論では「セット数が少なく設定されているんだな」と感じました。
私は、セット数の設定は「効かせられるまで」もしくは「納得いくまで」することが多くバラバラな感じで行うことが多くありました。
101理論は、1つの部位に対して多くて6セット、ということでした。
ということは、やはり基本は1種目2セットで3種目位までということになります。
例えば、胸なら、大胸筋の「上、中、下」を2セットずつまでということになります。
↓こちらの記事でも説明しています。

これからはセット数も2セットを基準にしていきたいと思っています。
マッスルコントロールが苦手な部位などは、3セットにしてフォローしていく感じにしていこうと思っています。
101理論は筋トレを面白くさせる
101理論から「短い時間でいかに効かせられるか」ということが大切なんだということを学んだ気がします。
マンネリしてきた私の筋トレに新しい「101理論」と言う要素が加わって
筋トレがさらに楽しく感じます。
101理論を実践していき、さらにレベルアップできるように頑張りたいと思いました。
皆様もいろんな理論を試されてみるといいと思います。
「継続は力なり」
では、ベイトでした。
自分の筋肉の質を調べてみたい方にオススメの記事


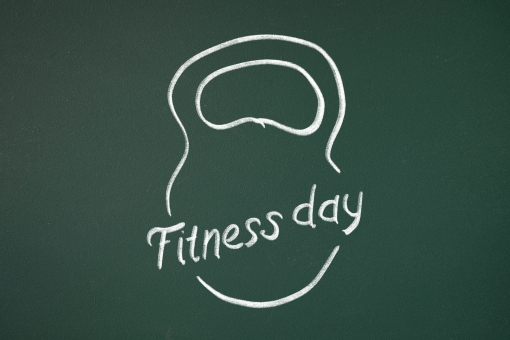






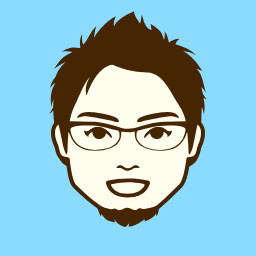


コメント